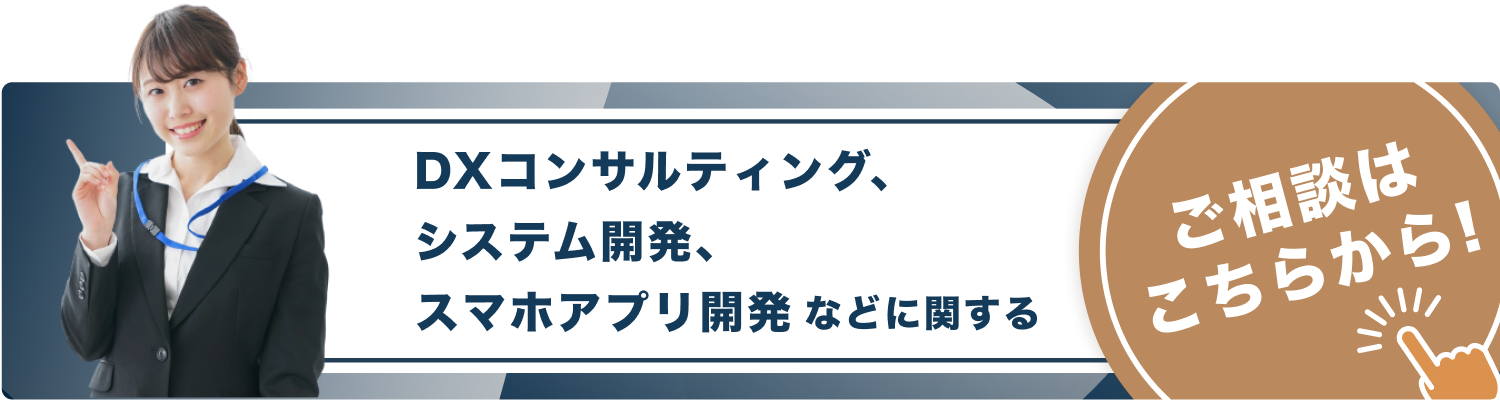目次
企業の成長を支える既存事業と、未来を切り拓く新規事業。どちらも重要でありながら、目的・評価・組織文化の違いを理解せずに同じ基準で運営すると、多くの場合うまく機能しません。
本記事では、既存事業と新規事業の本質的な違いを整理し、なぜ「同じやり方」では失敗するのかを解説します。さらに、実際の企業事例を交えながら、両立と共創を実現するためのマネジメントの要点を具体的に紐解いていきましょう。

新規事業と既存事業は何が違うのか?

既存事業と同じロジックで新規事業を運営しようとする企業は少なくありません。しかし、そのアプローチは多くの場合、期待外れの結果を生みます。なぜなら、新規事業と既存事業では前提条件そのものが大きく異なり、両者の本質的な違いを理解しないままでは、社内のリソースが空回りし、せっかくのイノベーションの芽が摘まれてしまうからです。
ここでは「目的」「市場環境」「リスクの扱い」「組織文化」「評価軸」「意思決定」という6つの観点から、新規事業と既存事業の違いを立体的に整理しましょう。
目的とゴールの違い
新規事業と既存事業では、スタート地点から目指す場所まで、あらゆる部分が異なります。
特に「何を成功と定義するか」の部分で、両者のズレは大きな影響を及ぼします。
| 項目 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 利益最大化・収益の安定確保 | 顧客課題の発見と仮説の検証 |
| 成果の定義 | 計画比達成、収益改善 | 学習の質とスピード、仮説検証の深度 |
| 成長の考え方 | シェア拡大、売上増 | プロダクト・マーケット・フィットへの到達 |
既存事業は、計画通りに進めることが成功の指標になります。一方で、新規事業においては、最初のゴールは「売上」や「黒字化」ではなく、仮説の精度を上げることそのものです。
ビジネスモデルと市場環境の違い
両者の違いは、土俵そのものが違うと理解するべきです。既存事業は「整った市場」での戦い、新規事業は多くの場合「まだ構造が定まっていない市場」での探索です。
比較ポイント
| 観点 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 市場構造 | 成熟しており競争関係が明確 | 不明確、存在しない場合もある |
| 顧客ニーズ | 既に特定済み・安定的 | 潜在ニーズの仮説構築から |
| モデル検証 | 済・最適化フェーズ | 未確定・構築中 |
新規事業では、「誰が顧客か」すら仮説です。課題がどこにあるのか、どうすれば解決できるのかを探るところから始まります。そのため、従来の常識や分析手法が通用しないことも多いのが現実です。
リスクと不確実性の度合い
「リスクがある」のは両者とも同じですが、リスクの中身と扱い方が決定的に違います。
リスクの本質的な違い
| 観点 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| リスクの性質 | 想定内の変動リスク | 想定自体が難しい不確実性 |
| 対応方法 | 綿密な計画、過去のデータ活用 | スモールテスト、段階的検証 |
| 成功確率 | 高め(過去に裏付けあり) | 低め(仮説次第で大きく変動) |
新規事業の失敗とは、「検証をせずに進めた結果、仮説が間違っていたと気づくのが遅れたこと」です。失敗ではなく学習として扱う視点が、新規事業を推進するチームの心理的安全性を支えるでしょう。
必要とされる組織構造と文化の違い
組織は目的に従って設計されるべきですが、多くの場合、新規事業に既存事業の構造が無意識のうちに適用されています。
組織と文化の主な違い
| 項目 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 組織構造 | 機能別・縦割り | フラット・越境型 |
| 意思決定 | 合議制・上意下達 | 現場裁量・スピード重視 |
| 組織文化 | 精度と安定を重視 | 柔軟性と挑戦を重視 |
また、挑戦に対してネガティブな反応が返ってくる環境では、挑戦そのものが抑制されます。新規事業には、評価されるべき行動や価値観がまるで異なる文化が必要でしょう。
成果の評価軸とKPIの設計思想
既存事業でのKPIは収益性や生産性など、予測可能な指標で構成されています。しかし、新規事業では測るべき対象が根本的に異なります。
KPIの設計比較
| 要素 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 成果の基準 | 利益・売上・コスト効率 | 検証回数・仮説の精度・顧客反応 |
| 評価対象 | 実績・安定性 | 行動量・学習量・変化率 |
| 評価指標の時間軸 | 月次・四半期 | フェーズごとに柔軟に変化 |
例えば、立ち上げフェーズで最も評価すべきなのは、何を学び、どんな気づきを得たかです。数値で評価するのが難しいため、定性指標も含めた設計が不可欠になるでしょう。
これは「評価を甘くする」ことではなく、「評価の軸を変える」ことだと理解する必要があります。
意思決定スピードとマネジメントスタイルの違い
意思決定の遅さは、新規事業において「致命的な遅延要因」になり得ます。
意思決定の構造比較
| 観点 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 意思決定の手法 | 稟議書・承認フロー重視 | 担当者裁量、最小限の承認 |
| マネジメント | 計画遂行の監督役 | 試行の支援者・壁打ち相手 |
| スピード感 | 精度を重視 | スピードを優先、あとから学習で補正 |
新規事業は、タイミングを逃せば競合に先を越されるか、ニーズそのものが消えてしまうこともあります。そのためには、マネージャーが「管理する立場」から「伴走する存在」へと役割を転換しなければなりません。
新規事業と既存事業で求められる組織・人材・文化は?

「人がすべてだ」と言われる新規事業において、どんなに魅力的なテーマや資金を用意しても、組織の設計や文化、アサインされる人材の思想が合っていなければ、事業は決して立ち上がりにくいのが現実です。
特に大企業では、既存事業で成果を上げた人材をそのまま新規事業に横滑りさせたり、ルールや評価制度も既存の延長線上に置いたままスタートさせるケースが少なくありません。結果として、失敗が過度に恐れられ、意思決定が遅れ、現場が疲弊していく構図が繰り返されています。
新規事業と既存事業では、求められる人の思考様式、組織の設計思想、インセンティブの方向性、そして文化的な前提までもがまったく異なります。
ここでは、そうした違いを具体的に掘り下げ、どのように分けて設計すべきかを検討していきましょう。
求められる人材の特性と行動原則
新規事業において必要とされる人材は、既存事業で高い成果を出した人材とは必ずしも一致しないこともあります。これは能力の優劣の問題ではなく、「適性(求められる思考・姿勢・行動様式など)の違い」である点に注意が必要です。
特に新規事業では、正解のない状態で意思決定を迫られるため、次のような要素を備えた人材がフィットしやすくなります。
- 未知の領域に飛び込むことを躊躇しない
- 完成を待たずに検証を始められる
- 他者からのフィードバックを歓迎し、自ら改善できる
- 結果が出なくても、試行の価値を自分で見出せる
- 上位者の承認を待たず、自走できる
いわば、「動きながら考えることができる人」が、もっとも適している人材像だといえるでしょう。
組織構造と意思決定プロセスの違い
組織の形と意思決定のスタイルは、事業の性格に強く影響を及ぼします。既存事業では「精度」が重視される一方で、新規事業では「スピード」と「柔軟性」が求められます。にもかかわらず、新規事業に既存の稟議・合議文化を持ち込んでしまうケースが少なくありません。
以下の表に、新規事業と既存事業における組織構造と意思決定の典型的な違いをまとめました。
| 項目 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 組織構造 | 縦割り・機能別・階層的 | フラット・小規模・越境型 |
| 意思決定 | 稟議制・合議・承認重視 | 現場裁量・迅速判断・後追い報告 |
| 判断基準 | 精度・失敗回避 | スピード・試行重視 |
| 指示系統 | 上意下達 | 自律分散型(任せる設計) |
事業開発を担う組織では、スモールチームでの試行錯誤と素早い意思決定ができる体制が求められます。特に立ち上げフェーズでは、失敗を恐れずに動ける構造でなければ、アイデアが絞り出される前に空中分解してしまうリスクが高まります。
評価制度とインセンティブ設計の考え方
新規事業の評価制度でありがちなのが、「数値目標が達成できなかった」ことを減点として扱ってしまうケースです。しかし、立ち上げ初期の段階で重要なのは、売上ではなく「どれだけ学び、どれだけ仮説を検証できたか」というプロセスです。
新規事業に適した評価設計の基本原則
- 成果よりも、行動と検証の量を評価する
- 定量ではなく、学習の質や変化への柔軟性を重視する
- 「売れたかどうか」ではなく、「売れる理由が見えたかどうか」に着目する
- KPIは固定せず、フェーズごとに動的に見直す設計にする
- チーム貢献(共創力)も評価対象に含める
また、インセンティブについても、既存事業と同じ評価基準(利益貢献、売上拡大)を設けると、チャレンジよりも保守的な行動が強化されやすくなるでしょう。
これは評価を曖昧にするという意味ではなく、「フェーズに応じて評価の軸を切り替える」という考え方です。
新規事業に既存事業の文化を持ち込むリスク
多くの企業において、文化は一貫して守られるべきものとされています。たしかに、企業文化は信頼や組織の統制において一定の役割を果たします。ただし、既存事業で長年機能してきた文化が、新規事業の推進を阻む要因になることもあるという視点を持たなければなりません。
例えば、次のような文化は、新規事業ではマイナスに働きやすくなるでしょう。
- 完成度を最優先する文化(プロトタイプの実装が遅れる)
- 正解主義(仮説構築や大胆なアイデアが出づらくなる)
- ミスを避ける文化(失敗を共有せず、学びが蓄積されない)
- 形式や段取りを重視する風土(動く前に承認が必要となる)
上記の文化は、既存事業では品質管理やリスク回避のために重要だったかもしれません。しかし、新規事業においては、スピードや柔軟性、学習優位の文化が求められます。
新規事業を既存事業と同じ基準で扱うと何が起きるか

新規事業の多くが、アイデア段階では期待されながらも、途中で頓挫してしまうケースが後を絶ちません。その背景には、「戦略」や「市場」の問題だけでなく、評価や意思決定の基準が既存事業のまま適用されてしまっているという構造的な問題が存在しています。
本来、探索型である新規事業には、不確実性を前提にした評価指標や意思決定の柔軟性が求められます。にもかかわらず、短期的なROIや黒字化、厳格な稟議プロセス、既存のKPIへの強引な当て込みなどが、新規事業の可能性を潰してしまう要因になっています。
ここでは、既存事業と同じ基準で新規事業を扱ったときに何が起こるのかを4つの視点から掘り下げ、見落とされがちなリスクとその本質的な要因を明らかにしましょう。
初期からROIや黒字化を求めてしまう
新規事業において、立ち上げ初期からROIや早期黒字化を厳しく求めるのは、成長の芽を摘む行為に等しいといえます。既存事業では当然の評価基準であっても、新規事業には適していません。なぜなら、新規事業はまだ「市場も価値も確定していない」状態からスタートするからです。
ROIを最初から問うことで生じる弊害
- 顧客理解や検証に使うリソースが抑制される
- 早期に売上を立てるための短絡的な企画に陥る
- 「当たりそうな企画」ばかりが選ばれ、革新性が失われる
初期段階では、ROIではなく「仮説がどれだけ検証されたか」「顧客のインサイトがどれだけ深まったか」といった探索の質そのものを評価軸とすべきです。成長に必要な時間と失敗を「コスト」ではなく「投資」と見なす視座が、経営側に求められるでしょう。
稟議・承認プロセスがスピードを奪う
新規事業は、不確実性の高い中で素早く試し、学びながら方向性を修正していくことが重要です。しかし、既存事業で使われている段階的で重層的な稟議プロセスがそのまま適用されると、スピードが致命的に落ちます。
典型的な問題点
- 上層部に全容を説明しなければ進まない設計
- 「成果が出てから進める」スタンスが新規事業には適合しない
- 社内調整にばかり時間が取られ、仮説検証が遅れる
結果として、スピードを重視すべきタイミングで社内稟議に数週間〜数カ月を要するという、本末転倒な状況が発生します。新規事業には、現場主導・小額・迅速な意思決定ができる特例ルールの設計が必要です。意思決定の権限委譲がなければ、どれだけ良いアイデアでも形にはなりません。
既存事業のKPIが新規事業を阻害する構造
多くの企業では、新規事業を既存事業部の管轄に置くケースがあります。その結果、既存事業のKPI――売上・利益率・顧客満足度など――が新規事業にも間接的に適用されてしまい、現場が守りの姿勢に陥る構造が生まれます。
構造の問題点
- 新規事業が既存ブランドを毀損すると見なされ、提案が却下される
- チャネルや人材が優先的に既存事業に配分され、新規が後回しになる
- 短期収益を重視する指標によって、時間をかけた検証が難しくなる
新規事業には、新規事業専用のKPIが必要です。それは「顧客インタビュー数」「仮説検証回数」「製品改善の頻度」など、初期段階の価値検証プロセスを可視化できるものにすべきです。既存の尺度をそのまま当てはめるのではなく、何を目指している事業なのかに合わせて設計し直す視点が不可欠です。
「失敗=悪」という評価が挑戦を止める
新規事業では、一定数の失敗が起きることが前提です。むしろ、複数の失敗を通じて本質的な市場や顧客課題が見えてくる構造であり、失敗は学習と同義です。しかし、既存事業で重視される「失敗しないこと」をそのまま基準にすると、挑戦そのものが組織内から消えていきます。
失敗がタブー視されると起きること
- 失敗が起きそうなアイデアは最初から提案されなくなる
- データが都合よく加工され、本質的な議論ができない
- 成功しか評価されない空気が、現場の創造性を奪う
挑戦を促す組織に必要なのは、「失敗を許す」ことではなく、失敗を評価する仕組みです。例えば、失敗を共有し組織知に変換する場の設計や、学びの質を評価するフィードバック文化などがそれにあたります。「挑戦すること」そのものを成果と認める価値観の転換が、経営層には求められます。
経営視点で見る新規事業と既存事業のリソース配分

多くの経営者が、新規事業の必要性を認識してはいても、実際にどこまで資源を投下すべきかという判断になると慎重にならざるを得ないという声をよく耳にします。確かに、将来性の見えない新規領域に対して、安定的に収益を生み出している既存事業の利益を振り分けるというのは、短期的には合理的な判断に映らないかもしれません。
しかし、変化の激しい市場環境においては、「既存事業の利益は永続しない」という現実と向き合う視点が欠かせません。利益を再投資して次の事業を育てるという発想がなければ、企業の持続可能性は徐々に損なわれていきます。
ここでは、経営の意思決定という観点から、新規事業と既存事業における投資判断の思想・資源配分の意義・成熟事業との共存戦略について見ていきましょう。
投資判断とROIの考え方の違い
新規事業と既存事業では、ROI(投資対効果)に対する捉え方が根本的に異なります。同じ評価指標を適用すると、新規事業への投資が常に割高に見えてしまうため、経営判断が過度に萎縮しやすくなります。
両者の投資判断の構造的違い
| 項目 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 投資の目的 | 効率性の最大化 | 将来の成長機会の獲得 |
| 投資回収の視野 | 1~3年の短期的視野 | 5~10年を見据えた中長期視野 |
| 成果の性質 | 定量化しやすく即効性あり | 定量化が難しく、探索型の成果が多い |
| 主な評価軸 | 売上拡大・利益率改善 | 顧客仮説の妥当性・検証スピード・市場性の見極め |
新規事業における投資判断では、定量的な収益シミュレーションだけでなく、「事業ポートフォリオ全体における位置づけ」や「将来の選択肢を拡張する意味」も含めて評価すべきです。ROIという単一指標での比較は、投資の意義を見誤るリスクがあります。
既存事業が新規事業を支える意味
新規事業は単独では立ち上がりません。リソース・ブランド・顧客基盤・人材など、既存事業が長年築いてきた資産を活用することではじめてスケーラブルな展開が可能になるケースが多く存在します。
以下のように、既存事業が果たす役割は極めて多面的です。
- 資金供給源としての役割
安定収益をベースに、新規事業への先行投資が可能になる - ブランドの信頼補完
顧客やパートナーに対して、新規事業単独では得にくい信用を与える - 既存顧客へのリーチ
既存の販売網・チャネルを活かして、初期段階から一定の顧客接点を確保できる - 人材・ノウハウの提供
オペレーション・法務・財務などのバックオフィス機能を共有することで、スピーディーな立ち上げを支援
新規事業はゼロから作るものではありますが、ゼロで動かすべきとは限りません。むしろ既存事業の資産を戦略的に活かすことで、リスクを下げ、検証サイクルを高速化することができるでしょう。
成熟事業との共存を実現するマネジメント戦略
新規事業の推進と既存事業の維持は、相反する構造を持つため、しばしば社内に無言の対立構造を生み出します。とりわけリソースが限られている中では、どちらに重点を置くべきかで経営判断が揺れがちです。
こうした状況を乗り越えるためには、共存を前提とした戦略設計が欠かせません。
以下の視点が鍵を握るでしょう。
- 役割を明確に区別する
既存事業=収益と安定、新規事業=将来の成長機会というように、それぞれの目的を社内で共有し、比較ではなく補完関係として認識させる - リソース配分のルールを可視化する
感覚や政治力ではなく、フェーズや進捗状況に応じた明確な配分ルールを設けることで、無用な摩擦を抑える - 経営が両者を繋ぐ橋渡し役になる
新規事業サイドに対しては応援と保護、既存事業サイドに対しては理解と敬意を持って接する姿勢が重要 - 組織の分離と連携のバランスを取る
出島やCVCなどを活用して一定の距離を取りながらも、完全に孤立させない設計が効果的
新旧の事業が足を引っ張り合うのではなく、お互いの特性を活かし合う設計こそが「両利きの経営」の核です。
新規事業と既存事業は両立できるのか?

新規事業の立ち上げが「既存事業との対立」になってしまう企業は少なくありません。新しい試みを始めようとすると、既存の組織や制度、価値観がブレーキになり、前に進めなくなり、結果として立ち行かなくなってしまう例も多く見られます。
ただし、原因のすべてが「社内政治」や「保守的な文化」にあるわけではありません。そもそも新規事業と既存事業は求められる役割も、評価軸も、動き方もまったく異なる存在です。つまり、対立は構造的に起きやすく、放置すれば摩擦や対立が慢性化しやすいのは必然だと言えます。
一方で、両者は本来、相互補完的な関係であるべきです。既存事業が土台となり、新規事業が次の柱を生み出す。この「両利きの経営」を実現するためには、両立を前提とした設計思想と仕組みが不可欠です。
ここでは、衝突の構造的要因、共食いを回避しながらシナジーを生む設計、そして出島戦略や内部インキュベーションの使い分け基準について、実務に役立つ視点で探っていきましょう。
なぜ新規事業は既存事業と衝突するのか
新規事業と既存事業の衝突は、偶発的に起きているわけではありません。両者の存在目的が違いすぎるため、評価軸・スピード感・使えるルールまで噛み合わず、自然と摩擦が生まれてしまう構造にあります。
衝突が起きる主な構造要因
- 目的の違い
既存事業は「安定的な利益の確保」、新規事業は「将来の成長機会の創出」がゴールであり、守るべきものと壊すべきものが異なる - 組織の論理の違い
既存事業は「失敗を避ける」文化、新規事業は「試行錯誤を評価する」文化が必要とされる - 資源配分に対する認識の違い
既存事業側から見れば、新規事業は「成果が見えないのにコストばかりかかる存在」となりやすい - 成功体験の固定化
過去の成功パターンが、新規事業に対して「それはうちのやり方ではない」と拒絶反応を引き起こす
衝突が起きるのは、感情や人間関係の問題ではなく、制度設計・文化・評価基準が分離されていないための必然的な結果です。
カニバリゼーション(共食い)を避けながらシナジーを生む設計とは
新規事業が成功し始めると、既存事業とのカニバリゼーションが懸念されるようになります。この段階で、新規事業側に制限をかけてしまう企業も少なくありません。
しかし、内部競合を過度に恐れるあまり、本質的なシナジーを生む機会まで失ってしまっては本末転倒です。
シナジー設計のための実践的視点
- カニバリゼーションは一時的と捉える
一時的な内部競合を許容することで、新しい市場開拓の芽を潰さずに済む - 既存事業の強みを新規事業に橋渡しする
顧客基盤・ブランド・営業チャネルなどは、適切に接続することで新規事業の加速装置になる - 価値基準のすみ分けを明示する
KPI、評価制度、マネジメント体制をそれぞれに最適化し、「比べる」のではなく「共に育てる」体制を整える - ピアレビューや対話の場を制度化する
新旧事業の責任者同士が、相互理解と共創の余地を定期的に議論する仕組みが有効
カニバリゼーションを「害」と見るか「進化の過程」と見るかによって、組織の意思決定は大きく変わるでしょう。
出島戦略と内部インキュベーションの選択基準
新規事業の開発組織をどこに置くかは、経営にとって極めて重要な設計論です。本体組織の中で育てる「内部インキュベーション」と、社外に切り出して育てる「出島戦略」は、それぞれ異なる目的と向き不向きを持っています。
両者の使い分けを考えるための比較表
| 項目 | 内部インキュベーション | 出島戦略 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 組織文化の変革、既存資産の活用 | スピード重視の仮説検証、新規領域の探索 |
| 組織との距離感 | 本体組織の中で活動 | 本体とは切り離された独立組織で活動 |
| 評価制度 | 本体と連動しやすい | 独自のルール・人事制度を適用できる |
| スピード | 比較的遅くなりやすい | 意思決定が速く、柔軟性が高い |
| 向いているフェーズ | 事業化以降のスケール段階 | 初期の仮説構築・PoCフェーズ |
出島は単なる別働隊ではなく、「異文化・異能の受け入れ先」としての機能が重要視されつつあります。短期的な成果を求めるのではなく、数年単位での事業創出を見越した「育てる投資」として捉えることが肝要です。
事例で学ぶ:成功企業に見る両立とシナジー創出の実践例

新規事業と既存事業の両立は、理屈では理解できても、いざ自社で実践しようとすると壁にぶつかるケースが多く見られます。制度、組織、文化のいずれもが既存事業を前提として構築されている企業にとって、「両立の仕組み」をゼロからつくるのは容易ではありません。
しかし、既存の制約を乗り越え、成果を出している企業も存在します。それらに共通するのは、新規事業を既存事業の延長ではなく、「異なる前提条件を持つ別物」として認識しながらも、両者のつながりをあらかじめ設計していることです。
ここでは、日清食品の出島型D2C戦略、NTTドコモと39worksの内部連携モデル、小松製作所のIoTを活用した既存資産の変革という3つの実例から、両立・共創を可能にした仕組みを具体的に見ていきます。
日清食品のD2C展開に学ぶ出島型戦略
日清食品は、カップヌードルをはじめとする定番ブランドで長年市場をリードしてきた企業ですが、その既存ブランドと一線を画す形で、出島型のD2C事業を立ち上げたことが大きな転換点となりました。
代表的な取り組みである「完全メシ」や「With Wellness」は、健康志向・ミールソリューション・サブスクモデルといった新たな文脈に挑戦したD2C事業です。特徴的なのは、これらの事業が本体のブランドや組織の影響を最小限に抑え、EC主導・Shopifyを基盤とした俊敏な運営体制でスタートした点にあるでしょう。
出島型D2Cの特徴
| 視点 | 日清の取り組み |
|---|---|
| ブランド設計 | 既存製品と切り離し、別ブランドで展開 |
| 顧客接点 | EC・サブスクモデルを中心に設計 |
| チーム体制 | 小規模で意思決定が早いチーム編成 |
| 成功要因 | 検証→改善のループを高速で回せる設計 |
| 本体との関係 | オープンな連携はありつつ、運営は独立志向 |
このように、本体組織の制約を受けずに挑戦を行える構造を出島的に設計したことが、短期間での検証と改善を可能にした鍵となりました。結果として、新しい市場に対する柔軟なアプローチが可能になり、既存のブランド価値を毀損することなく新たな顧客層を獲得しています。
NTTドコモと39worksの連携モデル
NTTドコモは長らく通信インフラという成熟事業を主軸としてきましたが、39worksという社内起業制度を通じて新規事業創出に本格的に取り組んでいます。
39worksは、社員が自らのアイデアをもとに新規事業を提案し、実証・検証を経て、一定の成果を出せば本格的に事業化される仕組みです。失敗しても「失敗の価値を共有する場(FailCon)」が設けられ、挑戦そのものが組織にナレッジとして蓄積されるよう設計されています。
特徴的な仕組み
- 社員発のボトムアップ型新規事業制度
- KPIの達成に応じて事業化判断が行われる
- 失敗を前提とした「学び重視」の設計
- R&D部門や事業部門との連携体制が柔軟
また、39worksでの事業立ち上げを通じて得られた知見は、ドコモ全体の文化変革にも寄与しています。新規事業に挑む人材に裁量を与え、意思決定のスピードを尊重する体制が、既存事業側にも波及し、組織の敏捷性向上につながっているのです。
小松製作所のIoT活用による既存資産の変革
小松製作所(コマツ)は、重機メーカーとしての成熟した事業基盤を活かしながら、IoTやDXの導入により既存事業の価値を再定義することに成功しています。
代表的な取り組みである「スマートコンストラクション®」や「KOMTRAX(建機遠隔管理システム)」は、単に新しい技術を導入しただけではありません。既存顧客の課題を軸に、価値提供モデルそのものを転換させた点が大きな特長です。
IoT活用による変革ポイント
- リアルタイムな稼働データの取得と分析により、建設現場全体の生産性向上を支援
- 既存機械の提供価値が「モノ」から「サービス」へと進化
- ハードウェア事業に蓄積された信頼が、ソフトウェアやコンサル領域へ波及
- 顧客の課題解決視点での事業ドメイン再定義
特筆すべきは、これらの新規価値が既存の強みを起点としている点です。新規事業が「既存の否定」ではなく、「進化」として実装された好例と言えるでしょう。
新規事業と既存事業を分けて設計するためのポイント

新規事業の立ち上げにおいて、既存事業との「違い」を理解することは当然ながら、現場で本当に必要なのは、両者を制度・体制・運用のレベルでどう設計的に分けて運用していくかのノウハウです。理論や意識改革だけでは、現場の摩擦や混乱は解消しきれません。
現実には、評価制度やKPIの共用、予算の取り合い、リソースの非対称配分など、両者の境界があいまいなまま併存している状況が、新規事業の推進力を鈍らせています。
ここでは、制度・体制・運用設計の観点から、新規事業と既存事業を適切にすみ分けるための実践的ポイントを整理しましょう。
KPIと評価制度のすみ分け設計
新規事業と既存事業では、追うべき成果の性質が異なるため、同じKPIを適用すること自体が誤りです。特に新規事業では、短期的な売上や利益といった指標だけでは成果を測れず、学習や顧客理解の深度が重要な成果と見なされます。
評価制度すみ分けの考え方
| 観点 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| KPIの性質 | 安定的な売上・利益指標 | 仮説検証数、顧客接点数などの行動指標 |
| 評価軸 | 達成率、収益貢献 | 学習速度、検証プロセス、適応力 |
| 評価のタイミング | 半期・通期での固定評価 | フェーズごとの柔軟な見直し型 |
評価制度のすみ分けは、制度上の工夫にとどまりません。評価者の目線や価値判断そのものを変える必要があるため、マネジメント層が、新規事業特有の成果の見方を理解することも不可欠です。新規事業に求められる行動と成果をきちんと評価できる体制を、組織全体で支える仕組みづくりが鍵になるでしょう。
リソース共有マトリクスの活用法
新規事業が立ち上がる際に直面する大きな課題が、既存事業とどこまでリソースを共有すべきかという線引きの難しさです。特にIT・法務・営業など、共通インフラ的な機能は、共有と分離の判断を誤ると事業スピードが著しく低下してしまいます。
こうした課題に対し、有効なのが「リソース共有マトリクス」の活用です。
リソース共有マトリクス(例)
| 機能領域 | 完全共有 | 条件付き共有 | 分離推奨 |
|---|---|---|---|
| 情報システム | ○(セキュリティ担保前提) | – | – |
| ブランド資産 | – | ○(フェーズに応じて) | – |
| 財務・経理 | ○ | – | – |
| 法務 | ○ | – | – |
| 営業チャネル | – | ○(パイロット施策時のみ) | ○(既存事業と顧客・市場が競合する場合) |
| カスタマーサポート | – | – | ○(新ブランド設計時) |
このマトリクスを導入することで、どこを独立させ、どこを共用するかを経営・現場の両方が可視化して判断できるようになります。資源の取り合いを防ぎつつ、両立に必要な調整コストを最小限に抑えるための有効な設計ツールです。
フェーズ別に最適化する組織体制のつくり方
新規事業はフェーズによって必要な能力・役割・スピード感が大きく変わるため、固定された組織体制ではむしろリスクが高まります。立ち上げ時には少人数・裁量重視のチームが適していても、事業化が見えてくると体制の再構築が不可欠になるでしょう。
フェーズ別の組織最適化の例
- フェーズ1:探索・仮説検証段階
- 小規模(2〜4人)、職能横断型チーム
- 意思決定スピード重視
- 評価は学習量と行動量中心
- フェーズ2:事業化判断段階
- 専任責任者を配置し、リスクを取れる設計に
- 外部パートナーとの連携が加速
- 本体組織との調整業務が増加
- フェーズ3:スケール段階
- 業務分業体制を構築
- 既存事業と連携する機能が増加
- 成果指標も事業性重視にシフト
最も重要なのは、「一度組んだ体制で走り切るのではなく、段階ごとに設計を見直す運営設計を組み込んでおくこと」です。これにより、組織の柔軟性と成長スピードが両立しやすくなります。
外部パートナー・スタートアップ活用の考え方
自社内だけで全てを完結させようとすると、新規事業は動きが鈍くなります。特に探索フェーズにおいては、スタートアップや外部プレイヤーとの共創が、スピード・柔軟性・学習力の面で極めて有効です。
外部連携を成功させるためには、以下の視点が重要です。
- リスクではなく可能性から出発する
- スタートアップとの連携は、既存のルールでは測れない価値をもたらすことが多いため、形式的なリスク評価ではなく、「何を得たいか」に立脚することが肝要
- 連携モデルを複数持つ
- PoC型、CVC型、出資なしの共創型など、目的に応じて柔軟に連携手法を使い分ける
- 連携担当に裁量を持たせる
- 連携交渉においては、意思決定権を持つ担当者が前線にいるかどうかでスピードが大きく変わる
- 知財や成果の扱いを事前に明確化する
- 権利関係や成果の帰属が曖昧なまま進めると、後工程で大きな障害になりかねない
外部との連携は、単なる「足りない機能の補完」ではなく、自社にはない発想やスピード感を内側に持ち込む経営戦略と位置付けることが重要です。
トップマネジメントが取るべき5つのアクション

新規事業と既存事業の両立には、現場の努力や施策だけでは限界があります。制度や文化を変革し、両利きの経営を実現するためには、トップマネジメントが、明確な意志と設計思想をもって関与の仕方を設計する必要があります。
特に新規事業においては、あいまいなミッション、裁量なき責任者、評価制度の形骸化がよくある失敗パターンです。現場が動かないのではなく、動けるように設計されていないという構造的な問題を、経営側が率先して解消しなければなりません。
ここでは、経営層が実務として取り組むべき5つのアクションについて具体的に掘り下げていきましょう。
ミッションとリスク許容度の明文化
新規事業の現場で最も困るのは、どこまで挑戦してよいのかが不明確な状態です。失敗を恐れて動けないのではなく、失敗の許容範囲が見えていないことがボトルネックになっているケースが多く見られます。
そこで、経営陣が最初に整理しておくべきなのは、事業の存在目的(ミッション)とリスクの受容ラインを明文化することです。これにより、現場は責任の所在と期待値を理解し、挑戦に踏み出しやすくなります。
明文化の具体的要素
- 新規事業に期待する目的(例:5年後の柱育成、イノベーション文化の醸成)
- どこまでの失敗を許容するか(損失額、期間、評価への影響)
- 中長期でのビジョンと短期KPIとの優先順位
明文化は単なる資料ではなく、対話を通じた納得形成のプロセスとして位置づけることで、組織全体に一貫した理解が浸透していきます。
新規事業責任者の任命と裁量設計
新規事業においては、プロジェクト責任者の力量が成否を大きく左右します。しかし、人選が既存事業の延長線上で行われたり、責任ばかりで裁量が与えられていなかったりするケースが後を絶ちません。
経営が担うべき重要な役割のひとつは、責任と裁量のバランスを適切に設計し、組織として支える構造をつくることです。
裁量設計で重視すべき観点
- 選定基準の明確化(挑戦志向、仮説思考、巻き込み力)
- 組織横断の支援体制(調整役ではなく意思決定者として機能させる)
- 裁量範囲の明示(予算、チーム編成、方向性変更の自由度)
適切な責任者の配置と裁量の設計は、新規事業がスピード感を持って動ける基盤となります。任せるからには、失敗も含めて組織として受け止める覚悟が必要です。
評価制度の二重構造と柔軟性
既存事業と同じ評価制度で新規事業を測ると、高い確率で機能しなくなります。理由は明確で、時間軸・成果の性質・学習曲線が異なるため、共通の物差しでは公正な評価にならないからです。
ここで求められるのは、評価制度の「二重構造化」です。つまり、短期指標を追う既存事業と、中長期の成果創出を目指す新規事業とで、異なるロジックの評価制度を併存させる運用設計が必要になります。
二重構造評価の設計例
| 項目 | 既存事業 | 新規事業 |
|---|---|---|
| 主指標 | 売上・利益・シェア | 仮説検証数・顧客接点・N1インサイト |
| 評価頻度 | 半期・通年 | フェーズごとに再設定 |
| 失敗評価 | マイナス評価 | 学習として評価対象 |
この制度を運用するには、評価者自身の視座を変えるトレーニングや、役員・マネジメント層での相互レビューの場が効果的です。制度だけでなく、評価する人の意識が変わらなければ制度も形骸化してしまいます。
全社的なアラインメントを保つコミュニケーション設計
新規事業と既存事業がうまくいかない理由のひとつが、組織内での「目的のズレ」や「情報の断絶」です。新規事業を社内の一部だけの取り組みにしてしまうと、組織全体の理解や支援を得られず、内部での孤立や摩擦が起きやすくなります。
そこで必要なのが、全社的なアラインメントを生むためのコミュニケーション設計です。
有効な設計要素
- 定期的な全社向け報告・共有会の実施
- 役員と現場の対話機会(オープンミーティング、AMAなど)
- Slackや社内ポータルを活用した進捗と学びの見える化
- 新規事業の仮説・目的・意義をビジュアル化し継続発信
コミュニケーションは一過性ではなく、継続的に意味づけを行う「リズム」として組み込むべき仕組みです。経営層の言葉と行動が一致していることが、全社の信頼と共感につながります。
撤退判断を含めた意思決定ルールの設計
新規事業においては、始める以上にやめる判断が難しいという声がよく聞かれます。成功に至らない事業をいつ、誰が、どの基準で終了させるか。明確なルールがないまま運営されると、リソースを浪費し、組織の士気も下がる結果になりかねません。
したがって、立ち上げと同時に「撤退基準」を明確にしておくことが、健全な新規事業ポートフォリオ運営の土台になります。
意思決定ルールに必要な項目
- フェーズごとのマイルストーンと判断基準の定義
- 継続・修正・撤退の3択を含めた意思決定フレーム
- 経営会議での定期チェックイン機会の設定
- 「失敗」に対する組織的な受け止め方の共有
撤退はネガティブな結果ではなく、適切な探索の結果としての「進化」であるという共通認識を持てるかどうかが、長期的な挑戦力を左右します。
まとめ:新規事業と既存事業は対立ではなく共創へ

新規事業と既存事業は、性質も目的も異なるため、しばしば評価軸や意思決定の違いから、対立構造を生みがちです。しかし、それは本来あるべき姿ではありません。既存事業が持つ安定性と資産、新規事業が持つ柔軟性と可能性を、いかに補完し合うかがこれからの経営に求められる視点です。
両者を同じ土俵で評価しようとすれば、新規事業の芽は簡単に潰れてしまいます。一方で、新規事業だけを既存の枠組みから切り離して扱えば、既存事業側の不信感を招きます。だからこそ、両者を分けて設計しつつ、共創できる接点を意図的につくることが、両利きの経営を実現するカギとなります。
対立ではなく共創へ。その設計と実行の中心に、トップマネジメントの意思と構造設計が必要です。挑戦と守りを両立させる経営体制こそ、これからの企業に問われる真の競争力です。
新規事業の成否は、アイデアや人材だけでなく、「どのような設計思想でプロダクトを形にするか」に大きく左右されます。
GENEEでは、PoC・MVPフェーズからスケールを見据えた本開発まで、新規事業特有の不確実性を前提にしたシステム開発を行っています。
既存事業と切り離すべき部分、あえて連携させるべき部分を見極めながら、事業のフェーズに合わせた開発をご支援します。※なお構想段階・要件未整理の状態からでもご相談可能です。

-
 GeNEEの開発実績
GeNEEの開発実績製造業、小売業、流通業、印刷・出版業など、業界別のベストプラクティスを保持しています。
弊社の開発実績にご関心のある方はこちら一部公開可能な事例を掲載中
-
GeNEEの事業内容
現在、6事業を展開しております。お客様の状況や目標に合わせて、FITするソリューションを提供いたします
6事業の詳細はこちら
-
弊社主催セミナー
最大月に1回のセミナーを開催しております。毎回30名以上の方にご出席いただいております。
テック系のセミナーにご興味ある方はこちら月に1回テック系セミナー開催中
-
オウンドメディア
GeNEE は技術に関する情報発信を積極的に行っています。 弊社のお客様だけでなく、業界全体に貢献のできる品質の高い情報提供を心掛けています。
最先端テクノロジーの情報配信中
-
GeNEEの会社概要
ビジネスxテクノロジーxデザインの三位一体で、お客様の課題を解決する独自のアプローチをご紹介
創業から15年の実績
-
GeNEEの5つの特徴
なぜGeNEEはコンサルティングやシステム開発のプロジェクト成功率が高いのか。
競合他社との違いや優位性についてまとめております。GeNEEの5つの特徴
-
GeNEEへのお問い合わせ
DX/ITコンサルティングのご依頼やシステム開発・スマホアプリ開発のご相談はこちらのフォームからお願いいたします
お問い合わせフォームはこちら
-
GeNEEの資料をダウンロード
ご希望の会社様にGeNEEのパンフレットをお送りしております。
ITベンダーとの繋がりをお探しの方は是非お気軽にリクエストください。資料ダウンロードはこちら

コンテンツマーケティングディレクター
慶應義塾大学卒業後、日系シンクタンクにてクラウドエンジニアとしてシステム開発に従事。その後、金融市場のデータ分析や地方銀行向けITコンサルティングを経験。さらに、EコマースではグローバルECを運用する大企業の企画部門に所属し、ECプラットフォームの戦略立案等を経験。現在は、IT・DX・クラウド・AI・データ活用・サイバーセキュリティなど、幅広いテーマでテック系の記事執筆・監修者として活躍している。












 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
 >
>
.jpg) >
>
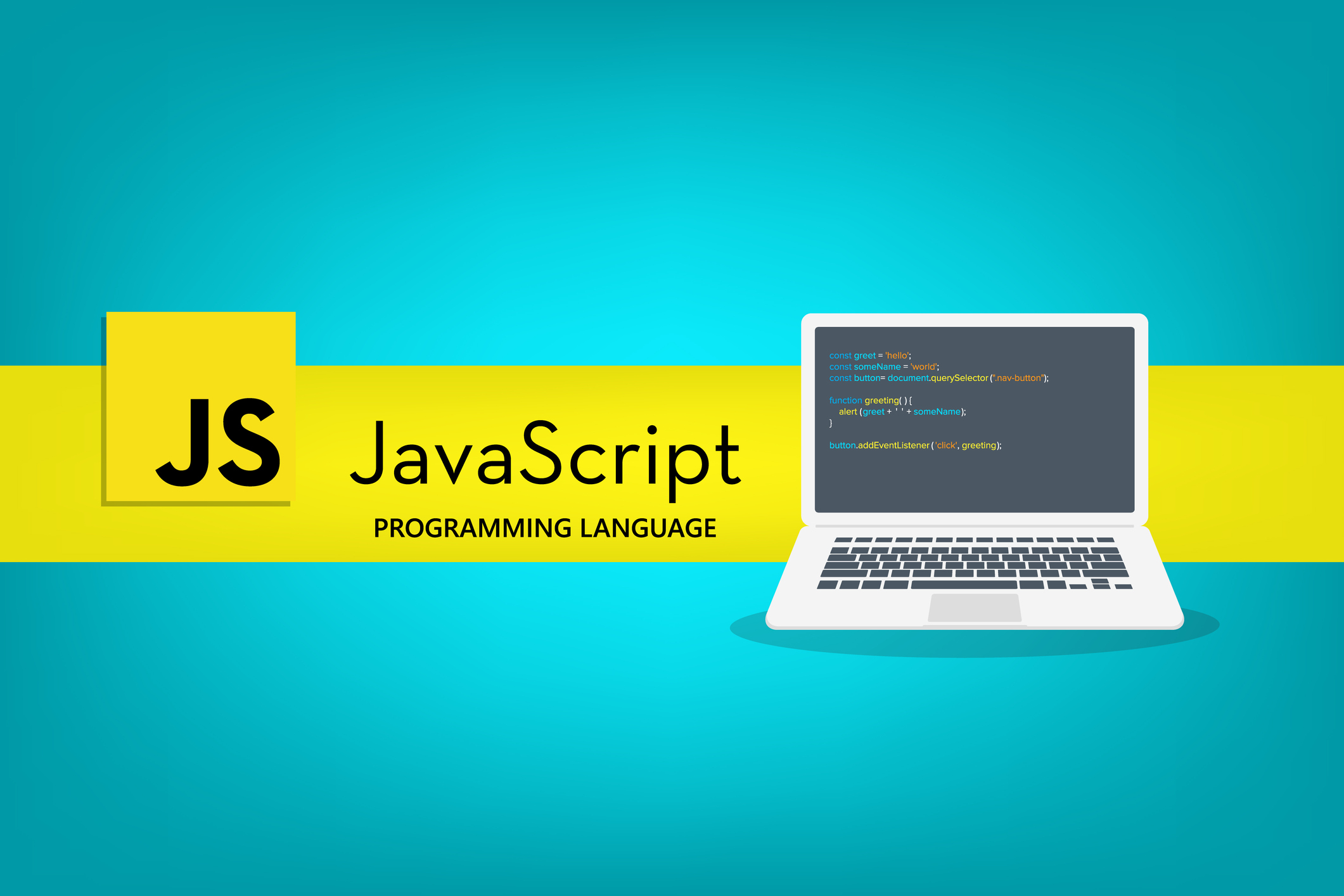 >
>
とは.jpg) >
>
 >
>