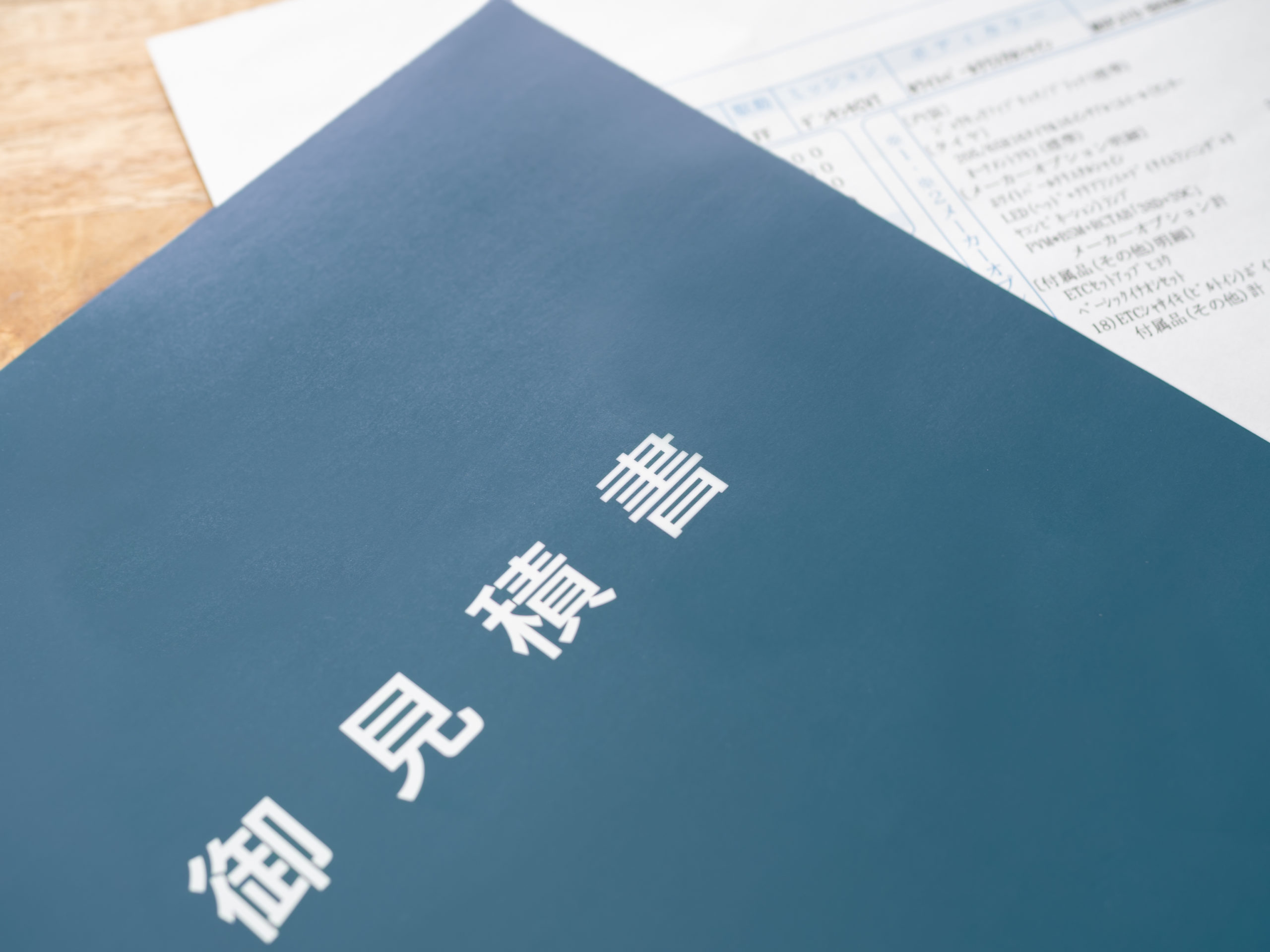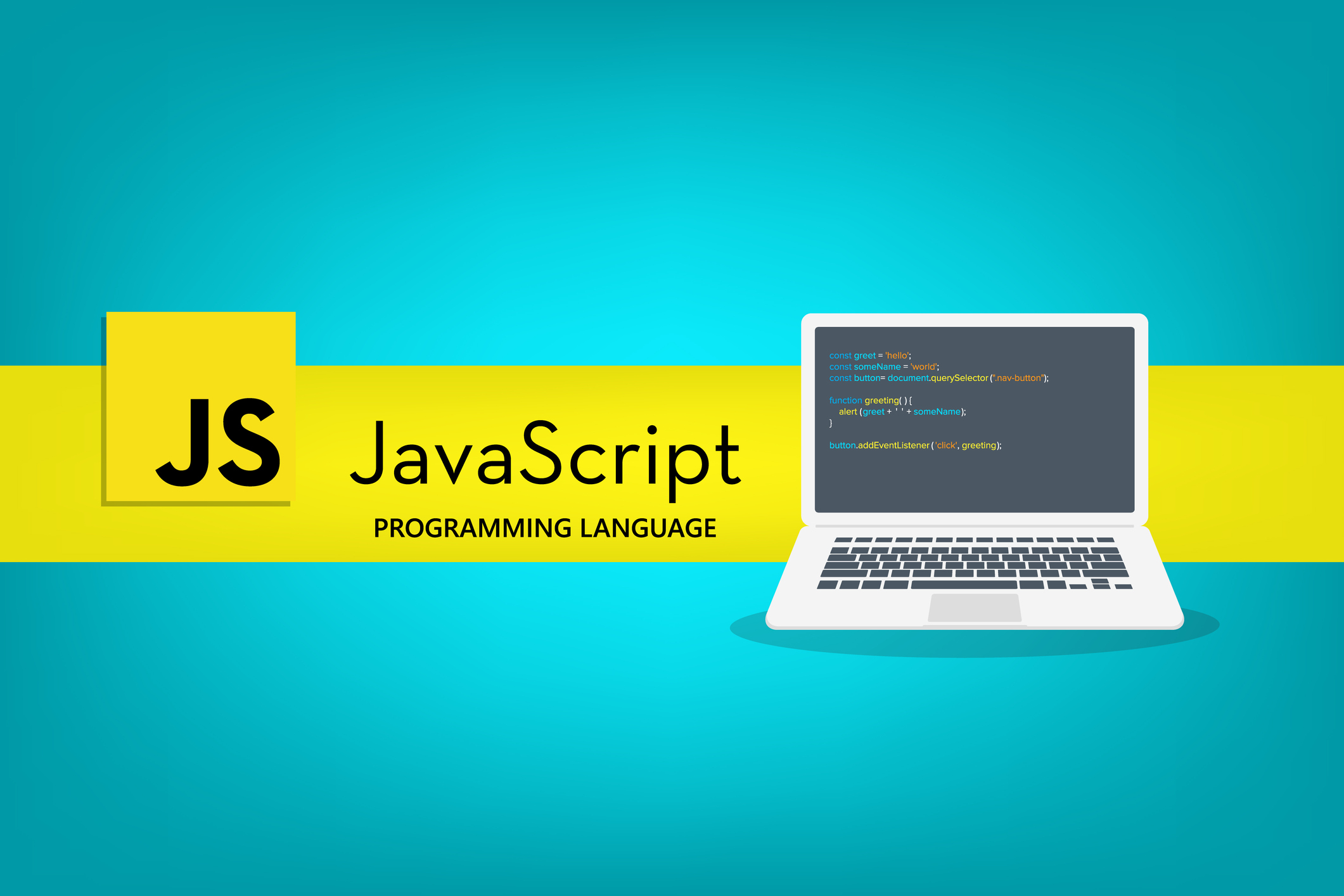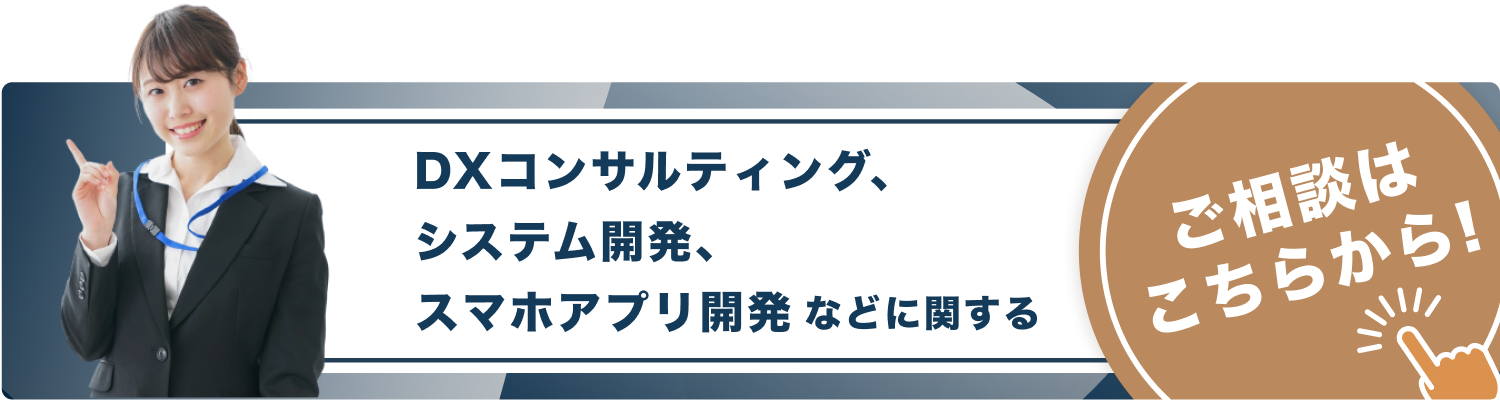目次
「DX」という言葉は徐々に見慣れたものとなってきましたが、なんとなくニュアンスは分かるけれど、正確に説明はできないという方も多いと思います。また、これまでのITという言葉との違いも気になりますよね。
本記事では、DXについて、ITとの違いやDXを導入した際のメリット、企業としてDXに取り組んだ事例から見る効果について解説していきます。
DX化とIT化の違い
DXとIT化の違いを理解する前に、それぞれの意味を把握しておくとスムーズです。
まずDXとIT化について見ていきましょう。
・IT化とは
IT化とは、コンピュータやインターネットなどの普及に伴って、暮らし・経済・社会がデジタル化することを指します。デジタル化によって、さまざまな業務が効率化されますが、例えば紙媒体で送付していた郵便物を電子書類に変換してメールで送れるようにした、などが例としてわかりやすいでしょう。このようにIT化で、これまでアナログで行っていた作業をデジタルにシフトし、業務の効率化やコストの削減を目指すことができます。
・DXとは
日本におけるDXは、2018年に経済産業省が取りまとめた「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」より、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(出典:「DX推進ガイドライン Ver.1.0(平成30年12月)」)と定義されています。
DX化を行うまでには、以下のデジタル化の3ステップが必要です。
①業務の一部分にデジタルツールを導入することで業務を効率化する
→ デジタイゼーション(デジタル化の第一段階)
②業務の効率化を目的として業務プロセスがデジタル化する
→ デジタライゼーション(デジタル化の第二段階)
③自社の業務効率化はもちろん、デジタルの力で世の中の変革を目的としたデジタル化
→ デジタルトランスフォーメーション(デジタル化の第三段階)
となります。
このように、DXは、単にデジタル技術を導入するということだけではなく、ビジネスのあり方や企業風土そのものも変革していくことを意味します。従って、まず企業をどのようにしていきたいかというビジョンが不可欠であり、IT部門だけが取り組むのではなく、全組織で取り組むことで、組織全体の変革を図っていくことが重要です。
※DX化を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
・具体的にDX化とIT化は何がどう違うのか?
結論から言うと、DX化とIT化の違いは「デジタル化を『手段』と捉えるか、『目的』と捉えるか」にあります。
具体的には、上記に挙げたように
DX化:デジタル化を「手段」として、製品・サービス・ビジネスモデルの変革を進めるもの
IT化:業務効率化を「目的」として、デジタル化を進めるもの
と言えます。
つまり、IT化はDX化を実現する際の手段の一つなのです。
DXを導入した際のメリットとはどのようなものなのか?
下記に掲げる3点が主なメリットとして挙げられます。
- 業務の効率化/生産性の向上
- 新たな価値創出による収益の増加
- BCP対策
それでは詳しくみていきましょう。
1.業務の効率化/生産性の向上
DXの導入によってシステムの維持費用や労力の無駄を省くことができ、コスト削減・効率化
を図れます。また、業務の効率化・自動化による企業の生産性の向上が期待できます。
2.新たな価値創出による収益の増加
DX化の過程において組織変革を行うことで、新たなビジネス・サービスが創出されれば、企業に新たな収益基盤を構築できる可能性が生まれます。
また、データを活用した精度の高い分析は顧客のニーズや利便性を拡充し、事業やサービスが本来の姿と異なる特性を持ち合わせることで、新しい価値創出に繋がっていきます。
3.BCP(Business Continuity Plan)対策
BCPとは、事業継続計画の意味で、災害などの緊急事態に事業を継続するための計画を指します。DXの導入でデジタル化を進めることは、BCP対策にも繋がります。
実際に昨今の新型コロナウイルスの流行により、多くの企業が業務変革を必要とされる中、既にデジタル化が進んでいた企業では、スムーズなリモートワークへの移行など、業務をする上で柔軟な対応が行われ成果を出すことができました。
このように、DXを導入することで、緊急時にも迅速で柔軟な対応が可能となります。
DXの企業別導入事例
・製造業事例
トヨタ自動車〜営業システムのデジタル化〜
トヨタ自動車は、『お客様との絆づくり』と『販売店の働き方変革』の実現に向け、オンプレ基幹システムとクラウド型CRM(顧客管理システム)の「Salesforce」を連携させ、顧客情報を一元化し横断的に活用できるようにしました。
これにより、クラウドが持つ拡張性や俊敏性といった特徴を最大限に活用し、販売会社の営業活動効率化が期待できます。
参照:
・建設業事例
清水建設株式会社
清水建設株式会社は、構造や性能をシミュレートするコンピュテーショナルデザインを設計段階から活用し、BIMデータを連携し、施工現場ではロボットや3Dプリンタを活用しています。
また、独自に開発した建物運用のデジタルプラットフォーム「DX-Core」は、エレベーターや監視カメラなどの建物設備や各種IoTデバイスと連携することで、建物運用管理を効率化したり、利用者の利便性や安全性を向上したりすることに貢献しています。清水建設は「DX-Core」を商品化、顧客への実装提案も開始しており、DXの成功事例として注目を集めています。
参照:
まとめ
いかがでしたでしょうか?
DXとIT化の違いからDXのメリット・効果まで理解を深めることはできましたでしょうか?
社会や市場の変化に対応していくためにも、あらゆる産業分野でDXが求められると同時に、例として挙げた製造業事例や建設業事例でもDXの必要性が高まってきています。
自社の既存のシステムや課題を理解した上で、今回ご紹介させて頂いた3つのステップを参考に、DXの実現を目指してはみませんか。
—————————————————————————————————————
システム開発、アプリ開発、新規事業立ち上げ、DX化の推進でお困りではありませんか?
日本全国には開発会社が無数にありますが、Webサービスやアプリサービスのスケール(規模拡大)を実現するビジネス推進力やシステムの堅牢性、可用性を意識した設計力・技術力を合わせ持つ会社は、全国で見ても多くはなく、弊社は数少ないその一つ。お客様のご要望通りに開発することを良しとせず、お客様のビジネス全体にとって最適な解を模索し、ご提案ができるビジネス×テック(技術力)×デザインの三位一体型のシステム開発/アプリ開発会社です。ITやDX全般に関して、何かお困りのことがございましたら下記の「GeNEEへのお問合せ」フォームからお気軽にご連絡いただけたらと思います。
—————————————————————————————————————





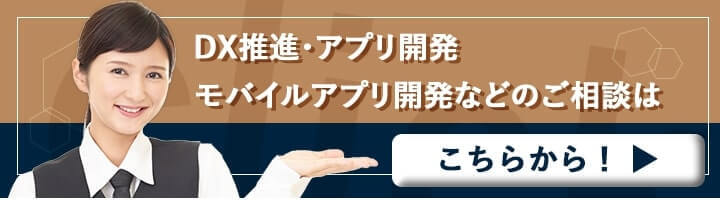



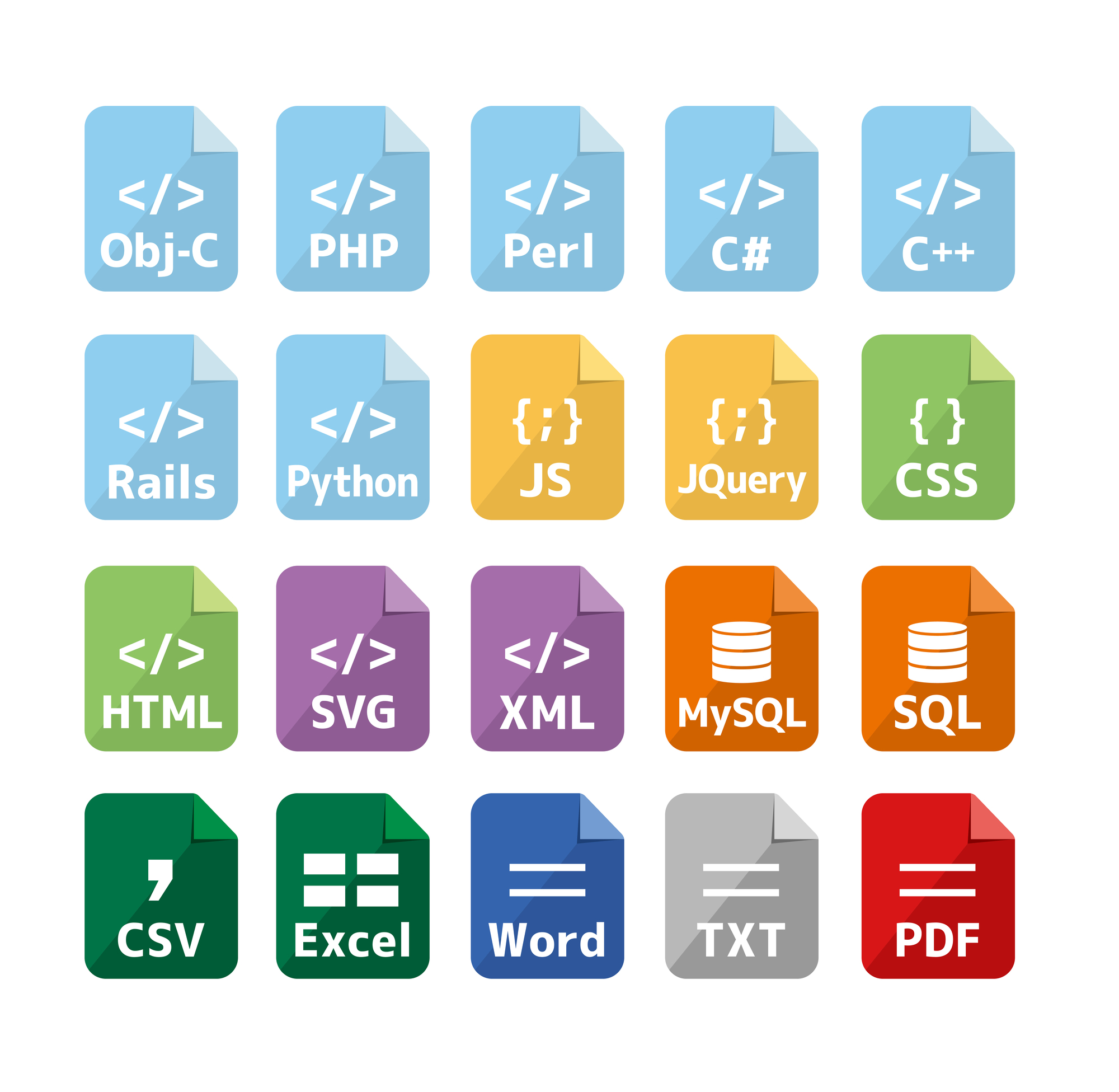




.jpg)
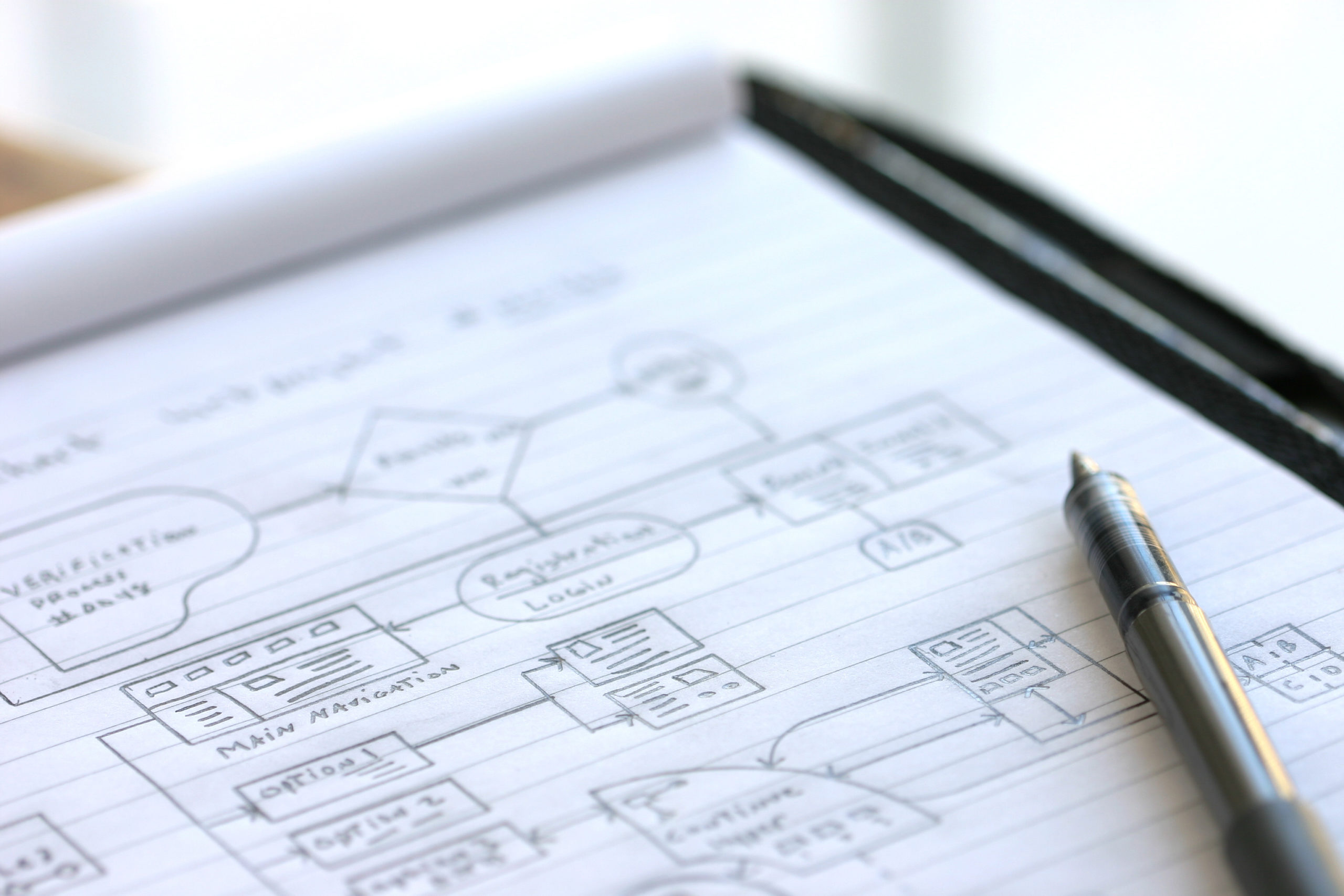

とは.jpg)