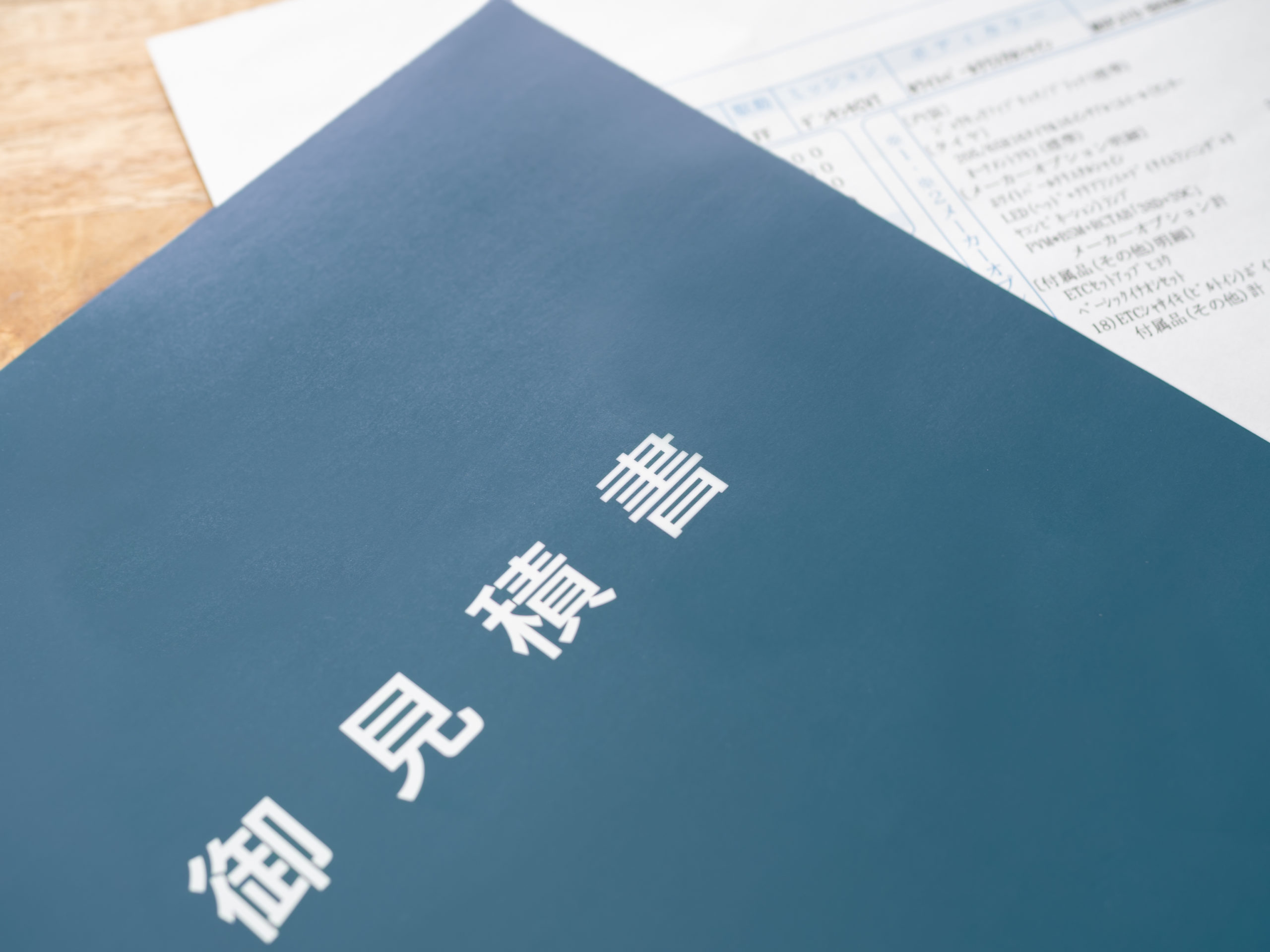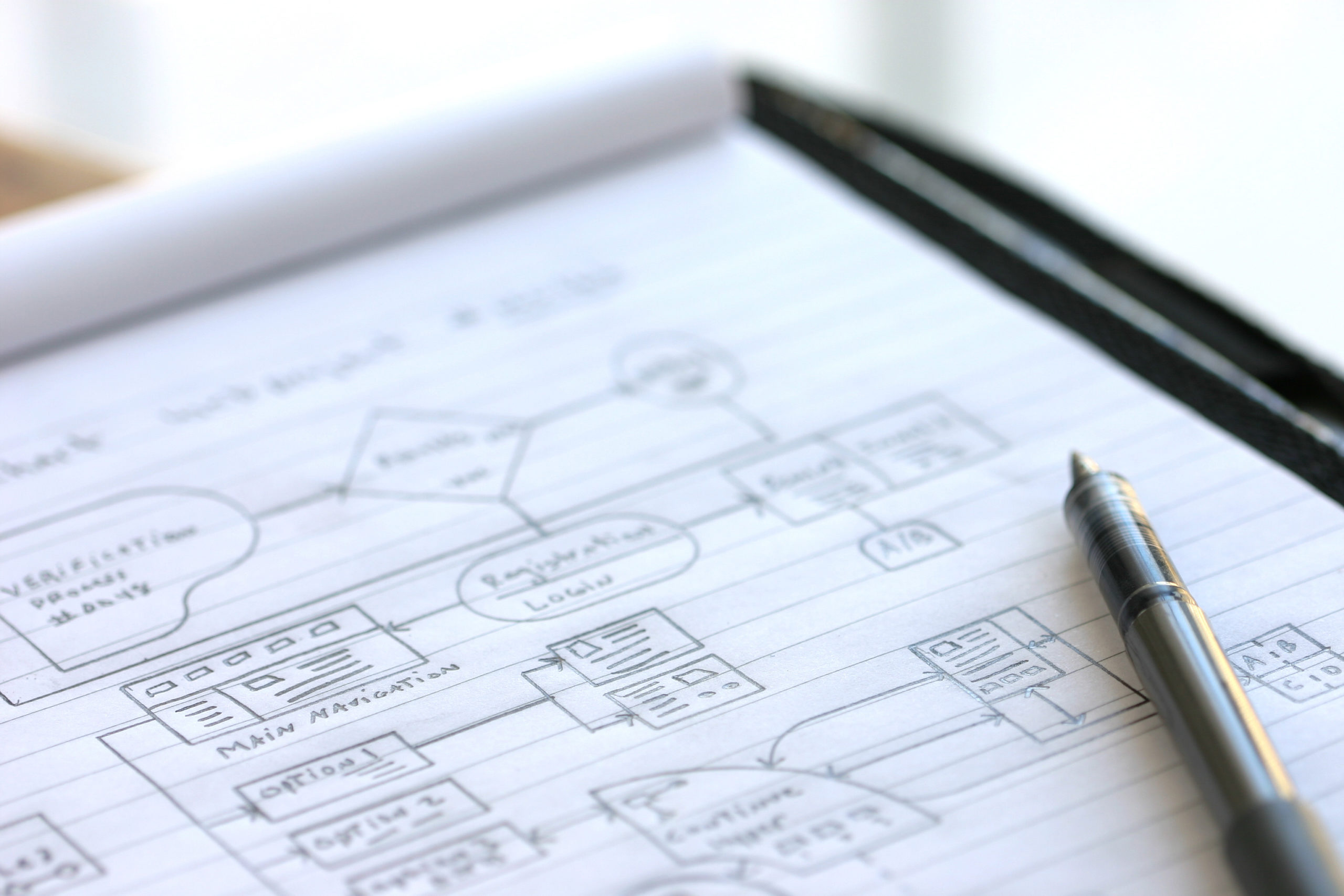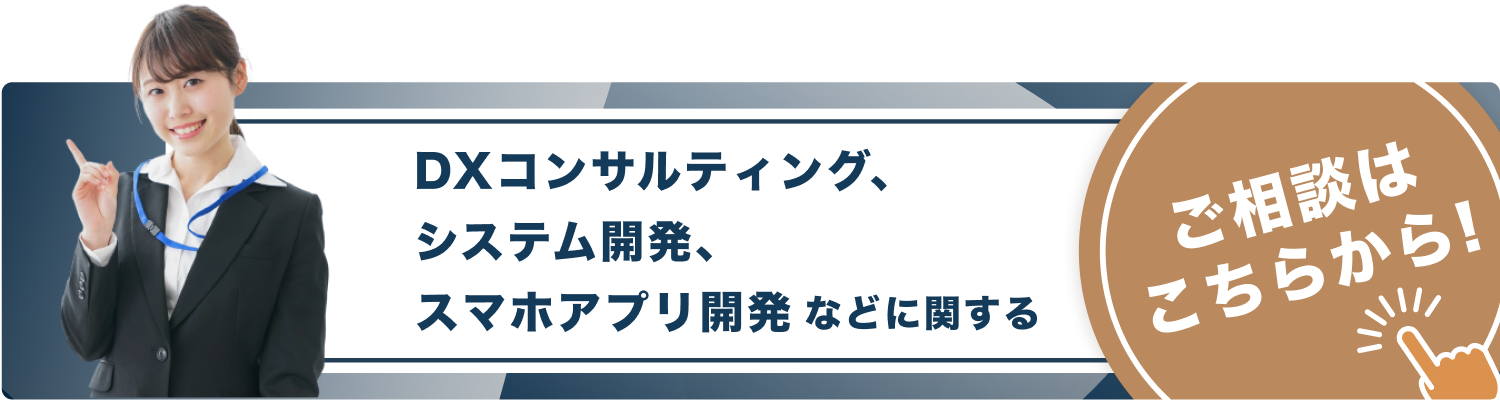目次
色々な業界でDXが進められる中で、
金融業界が直面するDX化への課題
まず、
以下に掲げる点が課題と考えられます。
- レガシーシステムから抜け出せない
- 収益全般の減少
- 進化する顧客体験に追いつかない
それでは、一つずつ説明していきましょう。
・レガシーシステムから抜け出せない
・収益全般の減少
しかし、現状この手数料だけで収益を伸ばすことは難しく、
それ故、
・進化する顧客体験に追いつかない
金融業界以外のサービスにおいても、
金融業界におけるDX化の活用方法
さて、ここまで述べてきたような課題に対して、DXを活用する方法を詳しく見ていきたいと思います。
以下に掲げる3点が主だった活用方法として考えられます。
- クラウドの活用
- RPAの活用
- AIの活用
・クラウドの活用
金融業界では、自社専用システムを構築するオンプレミスシステムが主流となっていますが、そこからクラウドシステムへの移行が有益です。銀行では口座をクラウドで管理するという、インターネットバンキングの導入が活用方法の一例と言えます。平日に店舗の利用が難しい顧客に向けた、手続き等もインターネットがあればどこからでもできるシステムは、現代社会では必要不可欠です。
また、顧客サービスだけでなく、企業内環境においても、顧客情報をクラウドで管理をすることで、業務の効率化と改善にも繋がるなどのメリットがあります。
・RPAの活用
RPA(Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)
という簡単な作業などを自動化する取り組みを活用することは、収益の減少に懸念のある金融業界では有効な手段と言えます。
日々の業務において、既存システムの刷新や利便性を高めるための戦略ももちろん必要ですが、そもそものDX人材が不足しているのが現状です。
それ故、RPAを活用することで、一部の簡単な作業に関しては人材と時間を削減できるようになるため、その分システムの刷新や戦略に時間を割くことができるようになります。RPAの活用は、早急に取り入れる必要性が高い内容と言えるでしょう。
・AIの活用
金融業界でDXを推進することで、データの取得および活用もしやすくなります。
特にAIを活用することで、人間には処理しきれない膨大な量のデータを活用でき、精度の高い予測や判断が可能になると言えます。さらには、AIが従来人間が行なっていた作業の一部を代わりに行ってくれることで、時間と労力に余白が生まれます。その余白で、AIではできない開発などを進めることができるようになるのです。
AIの活用の具体例としては、銀行業では融資が挙げられます。融資審査をAIを使った解析で行うことで、顧客分類ごとの審査ができるようになり、貸出先の拡大にも繋がっていきます。それ故、金融業界でAIを活用しない手はないと言えるでしょう。
DXを実現し成功した事例
セキュリティーの問題や長年の歴史から新しい発想に移行することが難しい企業の多い金融業界はDXへの遅れをとっていますが、そのような中でも少しづつDXを進め変革を遂げている企業はあります。その例を2社見ていきたいと思います。
・三井住友銀行
三井住友銀行はAIの活用により、業務の効率化を進めることができるようになりました。
元々、三井住友銀行には年間3万件ものお客様の声が届いており、仕分けや分析に10人の専門の担当者を設けていたそうです。しかし、膨大な量のデータの管理に作業が追いつかず、NECの独自開発したAI技術を導入することになり、これによって情報分析・分類・データベースへの登録までの一連の流れが自動化されるようになりました。これにより、頂いたお声からの業務内容やサービスの改善をするためのPDCAサイクルを以前より早くまわせるようになっています。
参照:NEC「株式会社三井住友銀行様」
・セブン銀行
まとめ
さて、いかがだったでしょうか。
システム開発、アプリ開発、新規事業立ち上げ、DX化の推進でお困りではありませんか?
日本全国には開発会社が無数にありますが、Webサービスやアプリサービスのスケール(規模拡大)を実現するビジネス推進力やシステムの堅牢性、可用性を意識した設計力・技術力を合わせ持つ会社は、全国で見ても多くはなく、弊社は数少ないその一つ。お客様のご要望通りに開発することを良しとせず、お客様のビジネス全体にとって最適な解を模索し、ご提案ができるビジネス×テック(技術力)×デザインの三位一体型のシステム開発/アプリ開発会社です。ITやDX全般に関して、何かお困りのことがございましたら下記の「GeNEEへのお問合せ」フォームからお気軽にご連絡いただけたらと思います。





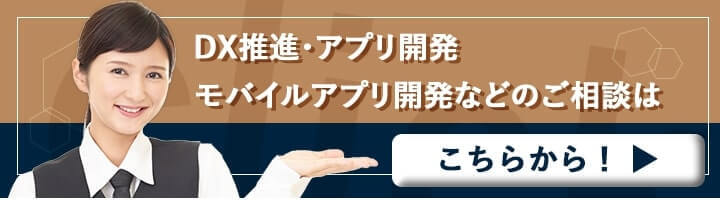
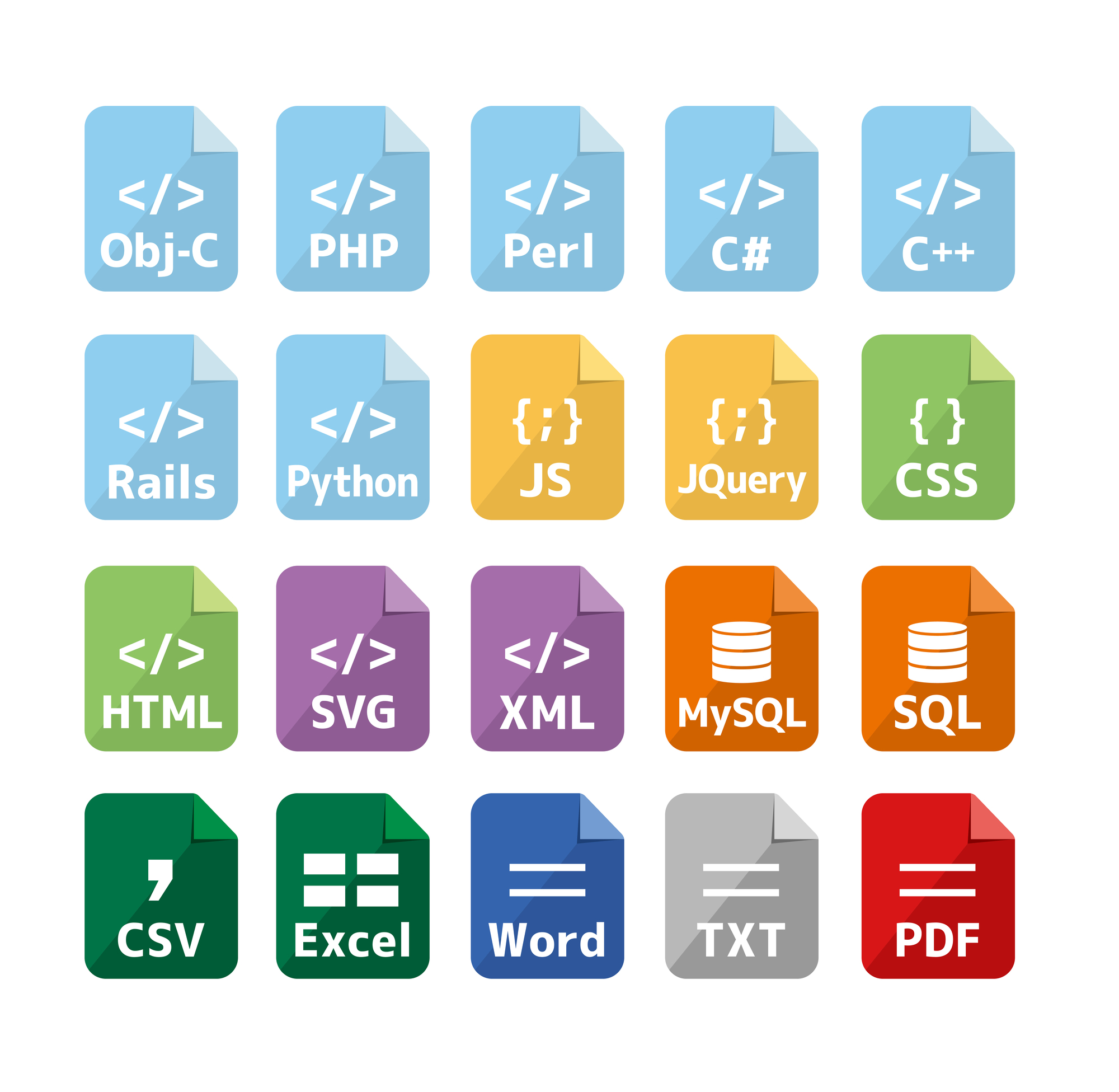








.jpg)
開発.png)